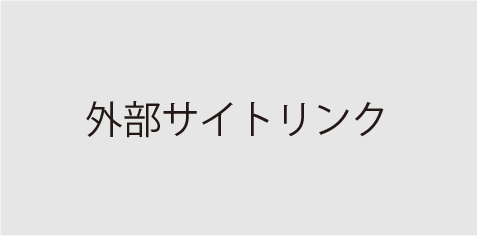2024.03.01

全国各地には「京の伝統野菜」のように、地域で長く受け継がれている野菜があります。東京にもこのような野菜があるのを知っていますか。
東京に伝わる伝統野菜の歴史
伝統野菜とは、その土地で古くから作られてきた野菜のこと。採種を繰り返す中で、その土地の気候風土に合った野菜として確立されました。地域の食文化とも深く関わっています。
栽培に手間がかる、大量に栽培できない、形や大きさがそろいにくい、日持ちしない、旬が限られているなどの理由で、生産は減少。しかし、1980年代半ばから「地産地消」が推進され、2013年には和食がユネスコ無形文化遺産に登録されました。これらの流れを受けて、伝統野菜を復活させて地域の特産野菜にする取り組みが、全国で見られています。
「大都市」のイメージが強い東京にも、伝統野菜は存在します。ここからその歴史についてお伝えします。江戸時代、世界一の100万都市として繁栄した江戸(※1)。参勤交代のため諸大名やその家族が大名屋敷に住み、その生活を支えるために職人や商人が多く集まりました。江戸は一大消費地となりましたが、野菜をはじめとする食料が圧倒的に足りませんでした。
※1)江戸の範囲や解釈はいろいろですが、現在の千代田区、中央区、港区、新宿区などが中心。23区全てが網羅されているわけではありません。
そこで幕府は、江戸近郊に畑を設けて農民に野菜を作らせました。また諸大名は、江戸近郊に下屋敷(倉庫や別邸の役割)を持っていたので、ここで国元から持参した種をまいて野菜を栽培しました。このようにして江戸の周辺には、いろいろな種類の野菜が存在するようになりました。

明治時代に入り、江戸とその近郊が東京と呼ばれるようになってもこれらの野菜の生産は続き、さらに種類も増えて、人々の食生活を支えてきました。1965(昭和40)年以降、農地や農家の減少や栽培に手間がかかることから、絶滅の危機に直面したこともありました。しかし、これらの野菜の生命を絶やしてはいけないと、伝統野菜として普及させようとの動きが始まりました。
2011年にJA東京中央会は、江戸と呼ばれる地域には畑がほとんどなく農業生産者もいないために対象地域を東京全体に広げて、これらの伝統野菜を「江戸東京野菜」と名付けました。ちなみに「江戸東京野菜」については、種苗の大半が自給または近隣の種苗商により確保されていた昭和中期までの「在来種」、あるいは在来の栽培方法を行っている野菜と、定義されています。
現在の栽培事例、販売ルート

江戸東京野菜は、52種類がJA東京中央会に認定されています(2023年11月現在)。それぞれの普及や改良には物語があり、興味深いものが多いです。季節は限られますが、JAの店舗で購入ができます。この中で代表的なものを紹介します。
練馬ダイコン
尾張大根(尾張は現在の愛知県)と、練馬の地大根との交配から改良されました。五代将軍徳川綱吉が、脚気(ビタミン不足が原因)にかかったとき、治療として食すため栽培を命じたと伝わっています。江戸時代中期の享保年間(1716~1736年)には、練馬大根と呼ばれたそうです。
伝統小松菜(ごせき晩生・城南)
八代将軍徳川吉宗が、鷹狩りに出かけた際に小松川村(現在の江戸川区)で、休息しました。ここで食べたすまし汁の中の青菜を気に入り、その名前を尋ねました。しかし、名前はなかったため、吉宗は「小松菜」と名付けたと言われています。
内藤カボチャ
大名内藤家の下屋敷(現在の新宿区)で栽培され、内藤かぼちゃの名前が付きました。宿場の名物になり、周辺農家でも生産されるようになりました。ちなみに他の土地で生産されたものは、その地名を取って角筈(つのはず)かぼちゃ、淀橋(よどばし)かぼちゃと呼ばれています。
馬込半白キュウリ(馬込半白節成キュウリ)
大井きゅうりとうりを掛け合わせて作られたのが、馬込半白きゅうり。大井きゅうりを栽培していた大井町(現在の品川区)が宅地化したため、馬込(現在の大田区)に生産地が移動したのがきっかけ。明治30年代(1897~1906年)頃から、栽培されました。その名の通り、白みがかかった緑色です。
寺島ナス(蔓細千成ナス)
文化文政年間(1804~1830年)に書かれた、武蔵野国の地誌(地理に関する書物)『新編 武蔵風土記稿』。この中に葛飾郡のなすについて「東・西葛飾領中にて作るもの。他の産に比すれば最も早し。よりて形は小さいなれど、早生なすと呼び賞賛す」とあります。葛飾郡寺島(現在の墨田区)で栽培が盛んだったため、寺島ナスの名前が付きました。
伝統野菜を使ったローカルフードレシピ

それでは、江戸東京野菜を使ったレシピを紹介します。
【ナスと豚肉のしょうが焼き】(寺島ナスを使用)
材料(2人分)
・寺島ナス 4本
・豚バラ肉薄切り 100g
・サラダ油 大さじ3
・おろししょうが 大さじ1
・みりん 大さじ2
・しょうゆ 大さじ1
・白ゴマ 小さじ1
・小ねぎ 少々
・(付け合わせ)レタス 少々、ミニトマト 2個
手順
①ナスは縦に4つ割りにし、火が通りやすいように切れ込みを入れて、水にさらす
②フライパンに油を熱し、水気を拭いたナスを入れて火が通るまで炒める
③おろししょうがと、食べやすい大きさに切った豚肉を加えて炒める
④豚肉の色が変わったら、みりんとしょうゆを回しかけて煮詰める
⑤皿に盛り、白ゴマと小口切りした小ねぎを散らす。レタスとミニトマトを添える
【小松菜と大根の中華風スープ】(伝統小松菜、練馬ダイコンを使用)
材料(2人分)
・大根 100g
・鶏がらスープの素 小さじ2
・水 400ml
・小松菜 2本
・めんつゆ 少々
・卵 1個
・ごま油 小さじ1
・小ねぎ 少々
・カマボコ 6切れ
手順
①鍋に鶏がらスープの素と水を入れ、いちょう切りにした大根を入れて煮る
②大根がやわらかくなったら、細かく刻んだ小松菜を入れて軽く煮立てる
③めんつゆで味を調える
④溶き卵を回し入れ、ごま油を垂らす
⑤器に盛り、小口切りした小ねぎとカマボコをトッピングする
【かぼちゃの蒸し物】(内藤カボチャを使用)
材料(2人分)
・内藤カボチャ 1/4個
・塩 適量
手順
①かぼちゃは皮の部分を洗い、ラップをかけて電子レンジで2~3分温める(切りやすくするため)
②少し大きめの一口大に切る
③せいろまたは蒸し器に入れて蒸す
④やわらかくなるまで10~15分蒸す
⑤食べるときに塩をふる
【キュウリの簡単おひたし】(馬込半白キュウリを使用)
材料(2人分)
・馬込半白キュウリ 1本
・塩 小さじ½
・しょうゆ、ポン酢など 少々
・かつお節 少々
・すりごま 少々
手順
①小口切りにしたきゅうりに塩をもみこむ。水気が出てきたら、両手で水気を絞る
②器に盛り付け、しょうゆやポン酢など好みの調味料を量を回しかけて、かつお節とすりごまを散らす
どれも、普段使っている調味料や道具で作れるものですね。江戸東京野菜が手に入ったら、ぜひ作ってみてください。
文 / 松原 夏穂